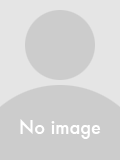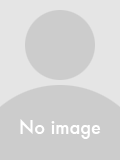|
・各自、教員が指定するマイコンボード、および電子部品を購入することが必須(8000円程度〜)
【モチベーション】
(1)IoT、電子工作、マイコンやセンサーを組み込んだ商品開発、実験に興味のある学生。
(2)ハードウェアだけではなく、ソフトウェア含め新しい技術が好きな学生。
(3)作るだけではなく、作ったプロトタイプを発信していくことに興味のある学生。
【プログラミング知識の前提】
(1)初歩的なプログラミングを理解していることが望ましい。
(2)プログラミングそのものやifやforなどの基本構文の説明は省略する予定。
(3)言語としてはJavaScriptを利用する想定。(Arduino言語も利用する可能性がある)
(4)プログラミング未経験者や自信が無い人は、ProgateのJavaScriptレッスン3までを事前履修必須。
【SNSアカウントの準備】
(1)演習でLINEを利用する予定のため、LINEアカウント必須。
(2)制作物はSNSへシェアを想定しているため、TwitterやInstagramなどの公開アカウント必須。
【その他条件】
(1)演習形式で進めるため、欠席は不可。
(2)最新話題をなるべく取り入れたいため、シラバスに記載の授業構成や技術トピックと必ずしも一致しない場合もある。
|