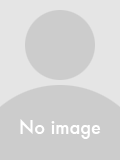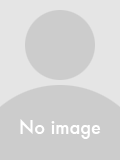|
まだ教科書には反映されていない、近年の研究成果を踏まえながら、中国とその周辺地域の歴史を概観します。いわゆる「通史」という形ではなく、幾つかのトピックを取り上げる形で歴史過程を概説します。前近代の歴史が中心とはなりますが、前近代社会の特徴が、近代から現代に至るまでの間に失われたのか、残存しているのかを考えることを糸口に、歴史を踏まえた現代社会の再検討を、各テーマごとに試みます。まずは、現代の中国やその周辺地域で生活する人々の、文化や社会を知ってもらおうと思います。そして、その背景にはどういった歴史があるのかを考えていく形で講義を進めます。
※授業内容は受講生の皆さんの意向により変更する場合があります。
|