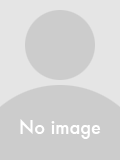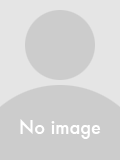|
ゲームエンジンである「Unity」は、ゲームの他、様々な分野で制作ツールとして使われている。本科目では、コンピューターグラフィクスの基礎的な素養として、Unityを用いたリアルタイムグラフィクス事例を学び、プログラミングとそれらを組み合わせて、どのような分野に応用することができるのか理解することを目標とする。また、Unity単体ではなく、他のデバイスとの連携や、複数のプログラミング言語を組み合わせた際の開発手法に関しても説明する。実際に作業をするというよりも広く知識を身につけることを主眼とする。
|