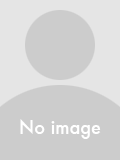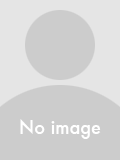|
平常評価と技能評価を複合的に成績として評価します。
平常評価=総評価の40%とします。授業出席、受講状態、アンケート等の提出状況にて評価します。
技能評価=総評価の60%とします。課題の提出状況、内容にて評価します。課題は各回授業の内容に沿って出題されます。単純な技能の卓越性のみではなく、授業内容を理解しているか、各々で技能向上を図ろうとしているか、などを評価します。クォーター末でのペーパー試験は実施しませんが、全課題をまとめた最終プレゼンを発表してもらいます。各作品の個別評価、及び最終プレゼンの評価の総合評価を技能評価とします。全課題への未着手、全作品の未提出に於いてはプレゼン発表の資格を失います。
|