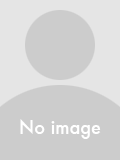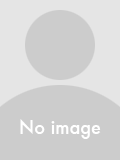|
教育社会学は、教育と社会がお互いにどのように影響を与え合っているかについて、様々なデータや理論を通じて分析する学問である。
この講義では、教育社会学のデータやものの見方を応用して、私たちに身近な進路選択やキャリアの問題について検討していく。
授業は、(1) 講義、(2) グループディスカッション、(3) 授業中に行うアクティビティで構成されている。(1)講義では、進路選択やキャリア形成に関連する教育社会学の知見を紹介する。(2) グループディスカッションは、講義の内容をふまえて、自分自身の進路選択やキャリア形成について意見交換してもらう。(3)授業中に行うアクティビティでは、授業内容に関するクイズやアンケートに回答し、それをシェアすることを通じて、授業内容に関して社会がどのような意識をもっているのかを考える。
さらに、毎回の授業後に小レポート、および、全授業終了後に期末レポートに取り組む。いずれも、授業の内容を自分自身の問題としてとらえ、私たちが当然だと思っていたことが実は当たり前ではないことに気づくこと、その気づきを通じて自身が大学で学んでいることの意味について再考するような内容になることを期待している。
|