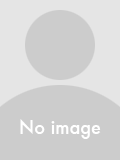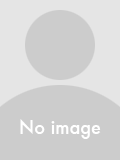|
ビジネスを成功させながら、社会の課題を解決する!?そんなことができるのでしょうか。この授業ではいま世界的な急成長分野である「ソーシャルビジネス」の考え方を学び、そのヒントを探ります。
社会問題の解決といえば・・NPOくらいは聞いたことがある。そんな学生も多いと思います。でもNPOって非営利だし、儲けちゃいけないんでしょ??・・いえいえ、世の中には儲かっているNPOってたくさんあります。人気就職先にもなっています。一般企業も、社会貢献をアピールするようになりました。ちゃんと儲けて、社会の課題を解決する企業が学生の人気を集めています。
近年は若い世代を中心に「社会起業家」と呼ばれる新しいタイプの起業家が増えました。画期的な事業を立ち上げて社会問題を解決しようと行動する人々がたくさんいます。この講座では全国のそうした事例を学び、ソーシャルビジネスの課題と可能性を学んでいきます。授業の中盤はほぼ毎回ゲストを招いて、話を聞いてもらいます。特に、この授業では日本の地方の話題について多めに取り扱います。地方でのキャリアや、リモートワーク勤務の可能性を考える切っ掛けになってくれたら嬉しいです。
この授業で大切にしているのが、「掛け合わせ」の発想です。普段学んでいる「映像・アート・プログラミング」などの技術を「社会課題解決」と掛け合わせる感覚を身につけてもらいます。本学の学生にもフリーランスや創業志望が増えていると感じます。ただ、何を起業したら良いのかと悩んでいる人も多いようです。その時に必要なのが「掛け合わせ」です。普段学んでいるデジタルコミュニケーション技術を、どうやって社会課題に掛け合わせるかという発想を持ってみましょう。起業のアイデアはそういうところに眠っているものです。本プログラムを通じて学生が新たな領域を開拓する後押しをしたいと思っています。
※なお、この授業では「ソーシャル・ネットワーク(いわゆるSNS等)」の話題は取り扱いません。
|