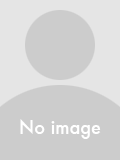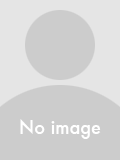|
本指導は、学生がアバター、メタバース、VTuber、生成AIといった先端技術を活用し、自ら設定したテーマに基づき卒業制作を主体的に推進することを目的とする。学生は、企画立案から研究・開発、成果物の完成、そして発表に至る全プロセスを経験する。これにより、専門性と総合力を高め、エンターテインメント分野に留まらず、教育、福祉、ビジネスなど多様な領域における課題解決や新たな価値提案に挑戦する実践的な問題解決能力と創造性を涵養する。学生は、この過程を通じて、自身の興味関心を深めるとともに、社会との接点を見出し、将来に繋がる価値創造を体験的に学ぶ。卒業制作で制作した成果物は、学内イベントとして2月の卒業制作展で展示する。この展示をもって、すべての学部履修を完了するものである。
|