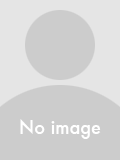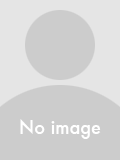|
卒業制作展における展示内容および準備過程を総合的に評価する。評価の比率は以下の通りである。
展示企画とコンセプト (30%):
学生が自身の卒業制作物の価値を最大限に引き出すための展示コンセプトを明確に設定できているか。
展示テーマと作品内容との整合性、独自性、および来場者への訴求力を評価する。
提案された展示空間(実空間またはオンライン空間)の活用計画が、作品の魅力を効果的に伝えるために熟考されているか。
展示表現と技術的完成度 (40%):
学生が制作した展示物(説明パネル、映像、インタラクティブ要素、デモンストレーション環境等)の質、および作品の技術的特徴やコンセプトを効果的に伝えるための表現力を評価する。
展示物の視覚的なデザイン、情報の整理、技術的な安定性(デモンストレーションのスムーズな実行など)を重視する。
来場者が作品の世界観や技術的な挑戦を理解しやすいように工夫されているか。
準備プロセスと主体性(平常点を含む) (20%):
平常点としての評価内容:
授業内での各課題(展示計画書の作成、説明資料の準備、中間レビューでの発表、リハーサルへの参加など)に対する取り組みの質と主体性を評価する。
設定された期限の遵守、および指示に対する理解度と実行力。
他の学生の発表に対する建設的な意見や、グループワークにおける協調性も考慮する。
上記の平常点に加え、展示準備期間全体を通じて、学生が計画的に準備を進め、発生する課題に対して主体的に解決しようと努力したプロセスを評価する。
プレゼンテーションとコミュニケーション (10%):
卒業制作展の会場(またはオンライン展示空間)において、学生が自身の作品について、来場者に対して明瞭かつ論理的に説明できるかを評価する。
来場者からの質問に対して的確に応答し、建設的な対話ができるコミュニケーション能力を重視する。
自身の制作活動に対する熱意や自信が、発表態度を通して伝わるか。
これらの評価項目に基づき、学生が卒業制作の集大成として、その成果を社会に向けて効果的に発信する能力を総合的に判定する。
※ 授業への出席は評価の前提条件であり、規定の出席回数(全8回中7回以上)に満たない場合は単位を与えない。また、展示準備および本番展示への参加は必須とする。
※ 上記の評価項目に関して、各回の授業で進捗確認と個別フィードバックを行う。学生は授業内での助言をもとに継続的に展示計画を改善し、最終的な展示に反映させることが求められる。
|